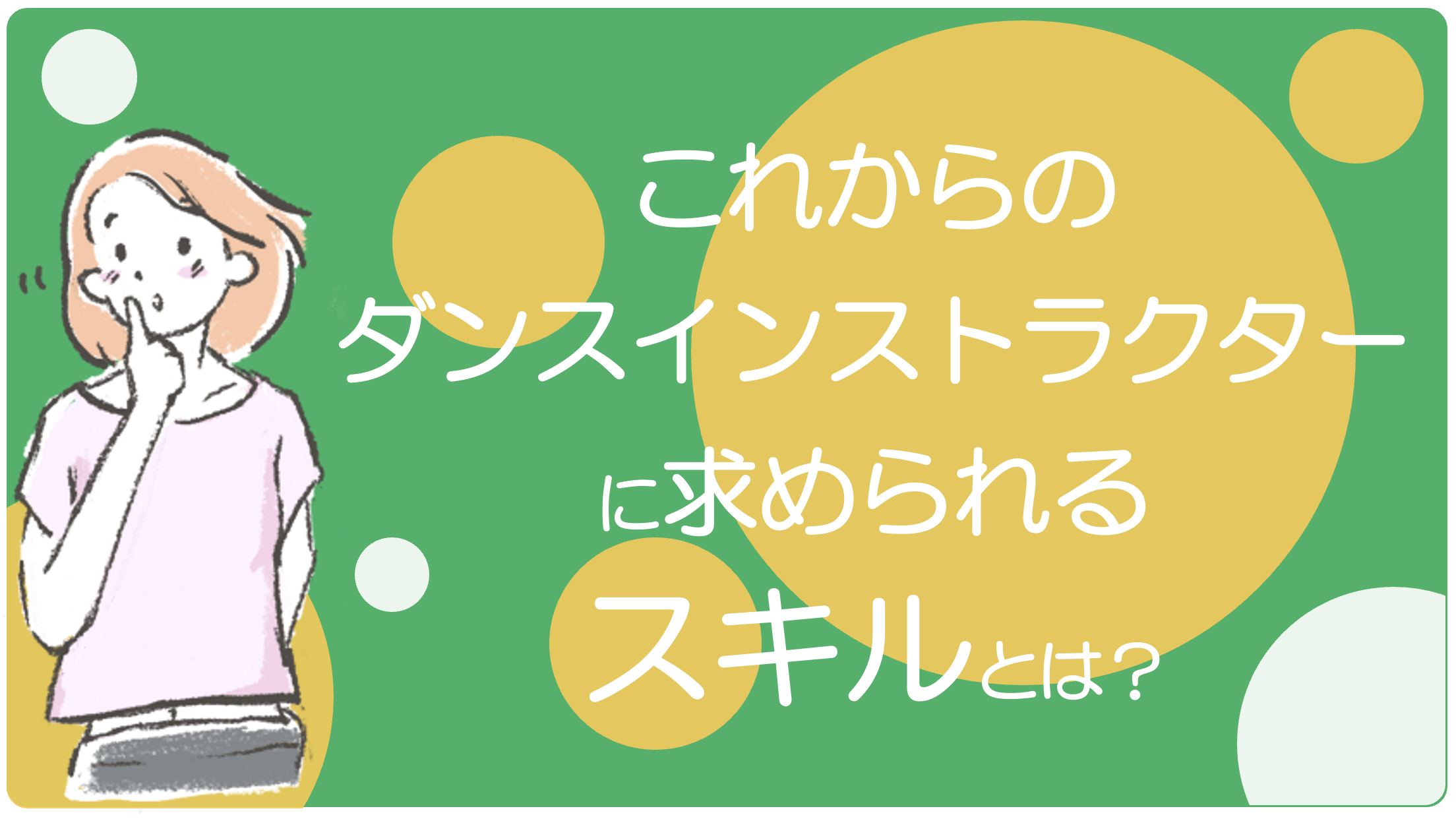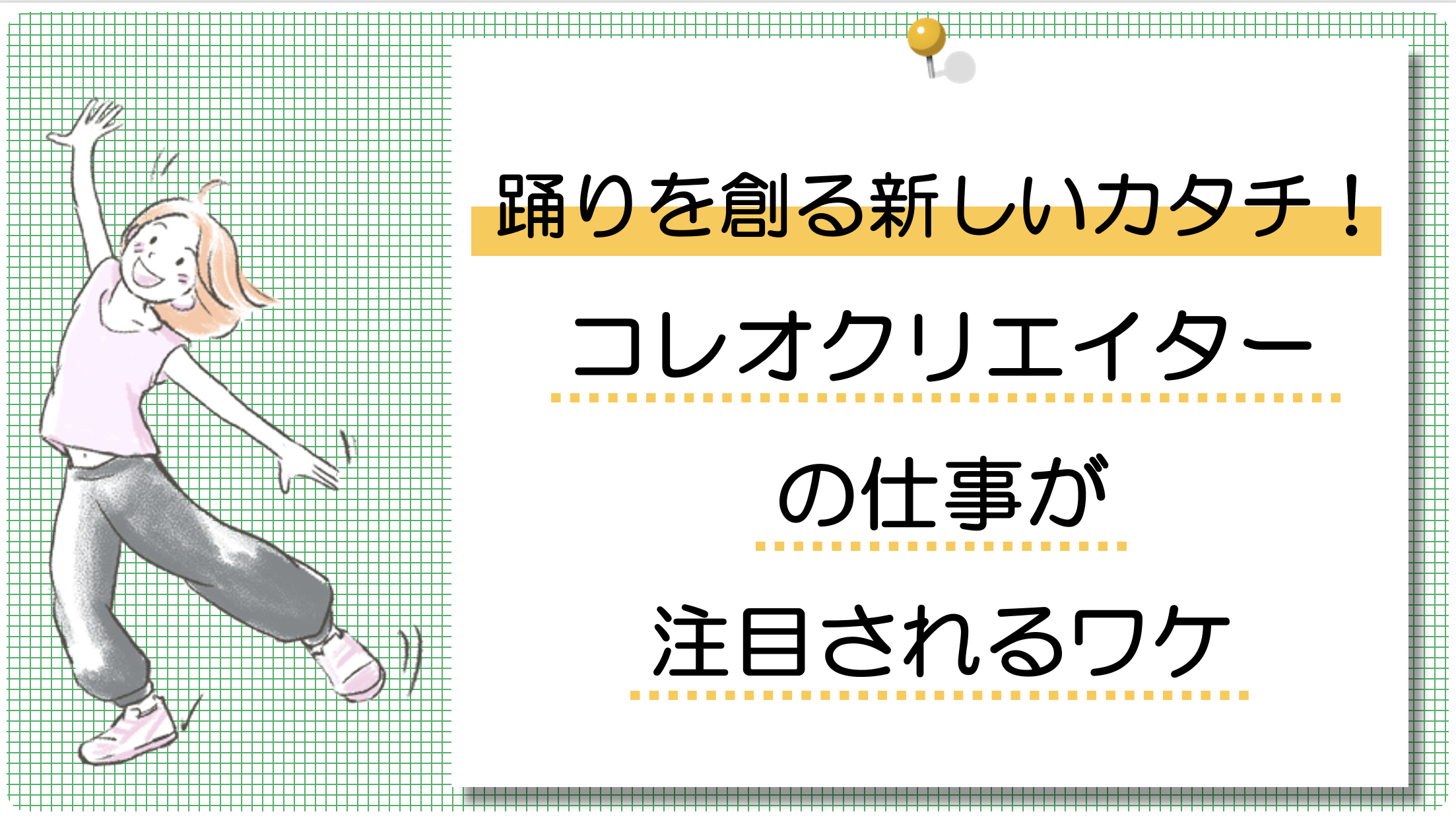ダンスインストラクターとして長く活躍するためには、時代の変化に適応しながら、自分自身のスキルを磨き続けることがより重要になってきます。特に、リアルの場とオンラインの活用、健康・フィットネスとの融合、マーケティング力、そして学び続ける姿勢が成功のカギを後押ししてくれるでしょう。今回は健康・フィットネス視点でのアプローチについて考察して見ました。
健康・フィットネス視点でのアプローチ
ダンスは、単なる「表現の場」だけでなく、健康維持や身体機能の向上にも大きな影響を与えます。より多くの人に指導するためには、フィットネスや健康に関する知識を持つことが大きな強みになります。
リハビリ・ボディメンテナンスの知識
ダンスによる怪我の予防や、ストレッチ・筋力トレーニングの指導
ダンスはときに激しい動きや、柔軟性を必要とした動きが伴うので、足首の捻挫や筋肉の肉離れ、膝の怪我などの可能性があります。そのため、インストラクターは怪我予防法の知識を身に付け、生徒に指導しましょう。
怪我予防法の一例は以下の通りです。
- 適切なダンスシューズ
- ウォームアップ
- ストレッチ
- 柔軟
- 筋力トレーニング
- 正しいフォームでのダンス
- 休息
- 栄養補給
これらの怪我の予防法を知るには、理学療法士のような専門家の指導を受けたり、ダンサー向けの解剖学に関する本やオンライン講座で学べたりします。
高齢者向けダンスプログラムの開発
最近ではシニアにターゲットを絞ったHipHopダンスで大活躍されているインストラクターも。年代にあったダンスプログラムを開発するのもダンスインストラクターとしての差別化の一つになるかもしれません。
たとえば、少人数短時間のレッスンでシニア層に人気の曲で踊り、クラス会や親睦会を定期開催するなど。高齢者が無理なく楽しめるプログラムにすることで、身体の調子にあわせてダンスレッスンを受けられます。
さらに、信頼を得るためにはシニアフィットネストレーナーといった資格を取得することも大切です。高齢者の身体状態を理解したうえで、レッスン内容を設定できるでしょう。資格の取得方法は講習会へ参加し、認定試験の受験です。
ストレッチ・コンディショニングスキル
ダンスを始めると必ずと言っていいほど、柔軟性や体幹を強化したい(強化することによってよりダンスが上達する)と言ったことにでくわします。それをうまく取り入れたレッスンプログラムを組めることはニーズに応えることになるでしょう。
ヨガ・ピラティス・筋膜リリースなどを取り入れたレッスンで差別化
レッスンにヨガやピラティス、筋膜リリースを取り入れると差別化を図れて生徒のダンス上達に役立つでしょう。
ヨガやピラティスのトレーニングは、可動域の広がりやぶれない軸づくり、スタイルを維持したままの筋力アップなどが期待。また、筋膜リリースのストレッチは踊ったあとの凝り固まった身体をほぐし、身体のケアに繋がります。ダンスレッスンのウォームアップやクールダウンなどに、ルーティンとして取り入れると身体のケアをしながら取り組めるでしょう。
また、ヨガやピラティスを生徒に指導するには、知識や経験が必要です。そのため、ヨガやピラティスのインストラクターの資格を取ったり、ワークショップに参加したりすることで技術習得を目指せます。他にも外部のプロに依頼することで、効率的にレッスン内でヨガやピラティス、筋膜リリースを生徒に伝えられます。
ダンサーに必要な身体のケアを学び、生徒の満足度を向上
ダンサーに必要な身体ケアは、身体づくりやストレッチ法などが挙げられます。
まずダンサーとしての身体づくりは、以下のような運動がおすすめです。
- 瞬発力:スタートダッシュ、全力ジャンプ、バーピー
- 持久力:ジョギング、ランニング、サイクリング
- 柔軟性:ストレッチ、ヨガ
- 体幹:プランク、腕立て
続いて、ストレッチ法はダンスのウォームアップとクールダウンで少し異なります。ウォームアップでは、筋肉をほぐし体温を上げる『動』のストレッチ。クールダウンでは筋肉の緊張をほぐす『静』のストレッチです。それぞれ行うことで、怪我の予防や、疲労回復に繋がりやすいとされています。
また、ストレッチだけではなくもみほぐしのケアを取り入れることで、さらに身体が軽く感じられるでしょう。指圧やマッサージボールといった器具を使うなど、気軽に取り組めます。このようなケアはあくまでセルフケアなので、身体が気持ちよく感じる程度で取り組みましょう。
これらをインストラクターが実戦して指導することで、生徒たちの満足度向上が期待でき、ダンス上達にも役立ちます。
栄養学の基礎知識
ダンサーや生徒に適した食事のアドバイス(エネルギー補給・疲労回復)
タンパク質や糖質、脂質などをバランスよく摂取することが大切です。特に肉や魚、乳製品や卵などのタンパク質は、筋肉を大きくしたり疲労回復を助けたりするので、運動している人にとって重要な栄養素といわれています。
また、脂質と糖質はダイエットでは敬遠されがちですが、エネルギー源になるので適量の摂取が必要です。摂取する際は揚げ物やお菓子などではなくナッツ類やオリーブオイル、果物や根菜類などの食材を選ぶとよいでしょう。
上記のような食事のアドバイスをすることで、生徒はダンスのレッスンのときだけではなく、日常生活のなかでも身体へ意識を向けられるでしょう。
食生活と運動のバランスを考えた指導ができるインストラクターは信頼度が増す
食生活や運動のバランスを知りたいと思っている生徒は多いのではないでしょうか。そのため、レッスン時にその点を詳しく教えてくれるインストラクターは、生徒から信頼が得られるでしょう。
知識は食事も運動も独学や資格、検定などで学べます。たとえば、食事であればスポーツ栄養士や管理栄養士、食事アドバイザーなど。運動であれば、パーソナルトレーナや理学療法士、筋トレインストラクターなどがあります。難易度はさまざまなので、自身が取り組めそうな内容から挑戦してみてはいかがでしょうか。
インストラクターの豊富な知識と経験が、生徒たちの疑問や悩み解決に繋がり、最終的にはダンス上達にも役立つでしょう。
このような視点を持つことで、ダンスインストラクターとしての指導力が向上し、より幅広い層にアプローチできるようになります。
【参照】
『ダンス部への提案〜新しいDANCEのススメ#4「ヨガ」「脱力」』
『ピラティスってなんでダンサーがやっているの?ダンサーがピラティスをすべき理由とは?』
『【基礎体力】ダンスが上手くなるための身体づくりの大切さを知ること』